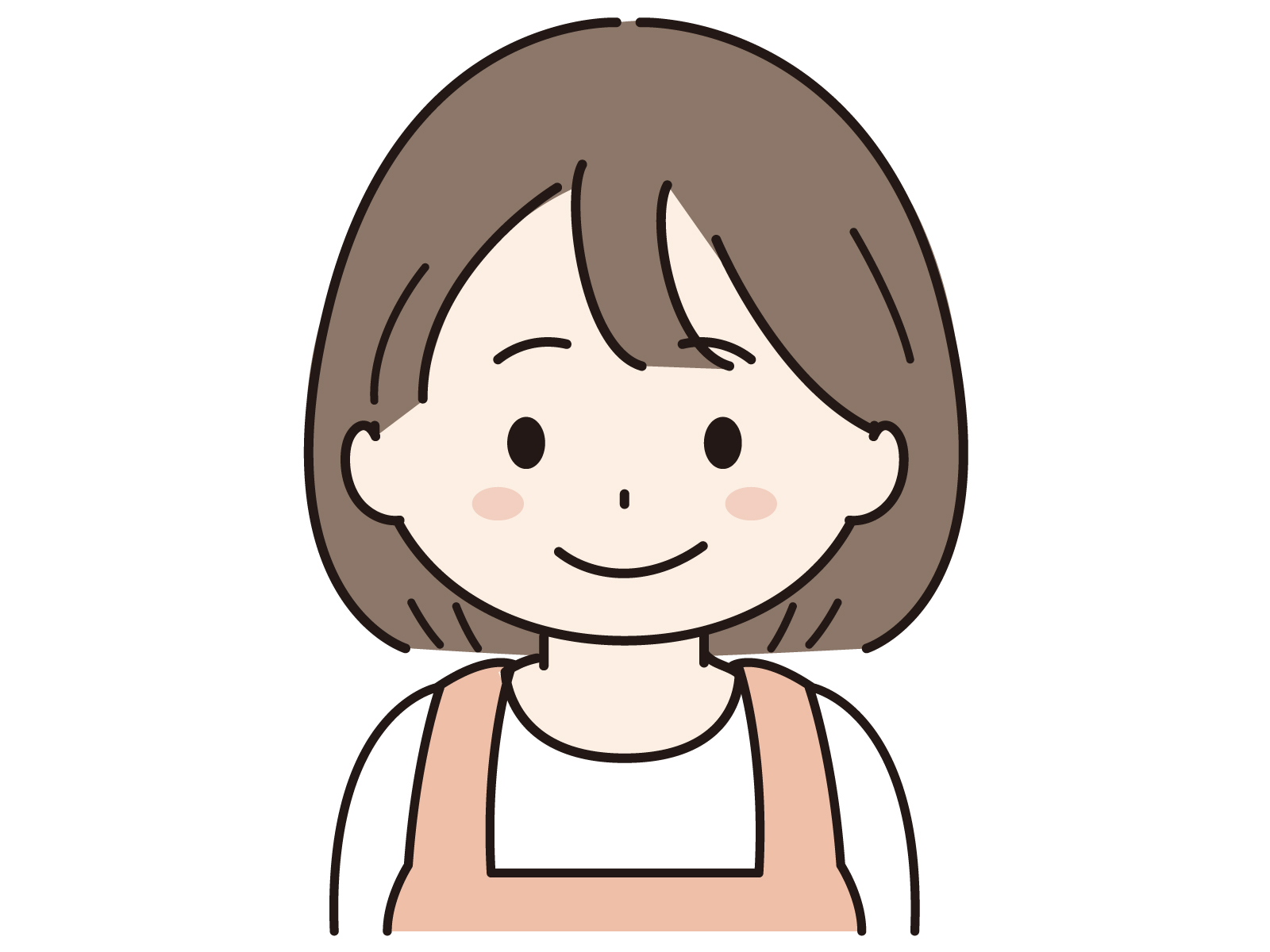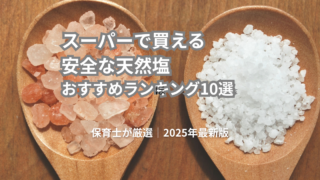SNSでは日々の子育ての気づきを発信していますが、
このブログでは、子どもの「やりたい」を尊重しながら育てる“食育”の実践法をお届けしています。
🍚「食育ってむずかしそう…」と思われがちですが、
実は今日のごはん時間を少し意識するだけで始められます。
たとえば、調味料や素材を見直すことも立派な食育です。
中でも塩は、味覚を育てる大切な要素のひとつ。
👉スーパーで買える安全な天然塩おすすめランキング10選|ミネラル豊富でおいしい塩【2025年最新版】
で、安心できる塩の選び方を詳しく紹介しています。
私は現役の保育士・学童支援員・モンテッソーリ教師です。
毎日、子どもの「やってみたい」という気持ちと向き合う中で感じるのは、
子どもの自立心は“食卓”から育つということ。
モンテッソーリ教育では、食事は“心と体を育てる大切な活動”とされています。
家庭でも、少しの工夫で食育を自然に取り入れることができます。
このブログでは、次の3つを中心に発信しています。
-
忙しい家庭でも無理なくできる食育の工夫
-
子どもが自発的に関われるモンテッソーリ流の環境づくり
-
家族みんなで安心して食べられる無添加の食材や生協の活用法
親にとっても最高の喜びです。
食を通して、親子がいっしょに育つ時間を大切にしていきましょう🌿
文章内に広告があります。
目次
食育とは?なぜ子どもに必要なの?
「食育」とは、食を通して“生きる力”を育てることです。
単に栄養を学ぶだけでなく、心・体・社会性をバランスよく育てる学びの時間でもあります。
1-1🍀 食育の基本的な考え方
食育の中心にあるのは、次の3つの力です。
| 育てたい力 | 内容 |
|---|---|
| 🍚 生きる力 | 食べることを通して、体を整え、元気に毎日を過ごす力。 |
| 💛 感謝する心 | 命ある食材・作ってくれた人への感謝を感じ取る心。 |
| 🌿 判断力 | 自分にとって何がよい食かを考え、選べる力。 |
食育の第一歩は、「何を食べるか」を意識すること。
どんな食材を選ぶかで、子どもの体も味覚も変わります。
👉【2025年】安全な油ランキング6選|スーパーで買える無添加を用途別に比較では、体にやさしく、子どもの発達にも安心な油の選び方を詳しく紹介しています。
子どもは、親の行動や言葉から“食の大切さ”を感じ取ります。
1-2🧠 なぜ子どもに食育が大切なのか
「食べる力」は、生きる力の土台。
特に幼児期〜小学生の時期は、味覚が育つ大切な時期です。
-
食べる意欲がわく
-
好き嫌いが減る
-
生活リズムが整う
-
体調を崩しにくくなる
この時期に「食べるって楽しい!」という体験を重ねることが、
一生の健康と心の安定につながります。
1-3🌸 モンテッソーリ教育に見る「食」の意味
モンテッソーリ教育では、食事は“自立への第一歩”とされています。
「自分で選ぶ」「自分で手を動かす」経験が、子どもの内面の成長を支えるからです。
たとえば──
-
スプーンやお箸を自分で使う
-
食卓を一緒に整える
-
盛りつけを手伝う
これらの小さな行動が、
「自分でできた!」という喜びと自信を育てます。
忙しい家庭でも、子どもが“自分で選ぶ食体験”を持てるように、
食材宅配を上手に使うのもおすすめです。
👉【コープデリ口コミ】子育て家庭に嬉しい時短と安心の生協?30年使った保育士ママが語るメリット
では、私が実際に利用して感じた生協の魅力を紹介しています。
そんな小さな一歩が、自立と感謝の心を育てる“食育”の始まりです😊
家庭でできる“食育”の始め方
食育は、特別な知識や時間がなくても始められます。
「毎日の食卓をちょっと見直すこと」が、子どもの心と体を育てる第一歩です。
2-1💡まずは「できることから」スタート
食育は“続けること”がいちばん大切です。
一度に完璧を目指さず、できる範囲で小さく始めてみましょう。
たとえば──
-
一緒に野菜を洗う
-
盛りつけを手伝ってもらう
-
「これ、どんな味?」と味の違いを話す
-
「ありがとう」と声に出して伝える
これだけでも、子どもは「食べるって楽しい」「自分もできた!」と感じます。
忙しい日こそ、できることを無理なく続けましょう😊
2-2🍎 食育を家庭で始めるときの3つのポイント
① 完璧を目指さないこと
「今日はレトルトでもOK」「野菜を1品だけ足す」など、ハードルを下げることが継続のコツ。
無理をすると続かず、食育が“義務”になってしまいます。
② “できること”を任せること
モンテッソーリ教育では、子どもの「やってみたい」気持ちを尊重することを大切にします。
たとえば──
-
ごはんをよそう
-
コップを並べる
-
テーブルを拭く
少しずつ“自分でできた”体験を積み重ねることで、自信と自立心が育ちます.
③ 食材に興味をもたせること
「この野菜はどんな形かな?」「塩によって味が違うね」と話すだけで、子どもの感覚が育ちます。
素材を変えるだけでも味覚の幅が広がります。
👉スーパーで買える安全な天然塩おすすめランキング10選|ミネラル豊富でおいしい塩【2025年最新版】
👉【保育士厳選】無添加出汁パックおすすめ15選|子どもに安心&毎朝の味噌汁にぴったり!
素材を選ぶときに“どう育てられた食べものか”を考えるだけで、子どもの感性は豊かになります🌱
2-3 家庭でできる小さな“食育の工夫”3つ
家庭での食卓は、子どもにとって最高の学びの場です。
ここでは、無理なく続けられる3つの小さな工夫を紹介します。
| 工夫 | 内容 | 関連記事リンク |
|---|---|---|
| 🍚 家で使う塩を見直してみる | 子どもと一緒に“味見”をして、自然の塩の味を感じてみましょう。味覚を育てる第一歩です。 | 👉 スーパーで買える安全な天然塩おすすめランキング10選|ミネラル豊富でおいしい塩【2025年最新版】 |
| 🥕 忙しい日は生協の食材を上手に使う | 生協の冷凍野菜やだしパックを使えば、短時間で安心ごはん。親子で料理も楽しめます。 | 👉 30年使ってわかった!コープの無添加食品おすすめ26選|保育士ママの本音レビューと宅配サービス比較 |
| 🍩 おやつも“学びの時間”にする | おやつも立派な食育。選ぶ・作る・味わう過程を楽しみながら、食への興味を育てましょう。 | 👉 【2025年無添加】体にいいお菓子、スーパーやコンビニですぐに見つける方法 |
完璧を目指さず、今日できることを楽しみましょう😊
🌿まとめ|家庭の食卓が、子どもの心を育てる
-
食育は「日常の中にある学び」
-
モンテッソーリの考えを取り入れて、“やりたい”気持ちを尊重
-
素材に触れ、味を感じ、感謝する時間を大切にする
忙しい家庭でも、無添加の食材や生協の食材宅配を上手に使えば、
無理なく続けられる「安心の食育習慣」をつくることができます。
年齢別に見る!子どもの発達に合わせた食育の進め方
子どもの発達段階に合わせた食育を行うことで、
「食べる力」だけでなく、考える力・感じる力・感謝する心も育ちます。
同じ“食育”でも、
2歳の子と10歳の子ではできることも関心も大きく違います。
ここでは、年齢ごとにどんな関わり方が効果的かを紹介します。
3-1 幼児期(2〜5歳)|五感で感じる“食べる楽しさ”を育てる
この時期の子どもは、見る・触る・嗅ぐ・味わうといった五感を通した学びが中心です。
食事を「教育」ではなく、「遊びや発見の時間」として一緒に楽しみましょう。
| 食育のポイント | 内容 |
|---|---|
| 🍅 感覚を使う | 野菜の形・色・においを観察し、「これ何の野菜かな?」と声かけする。 |
| 👶 自分でやる体験を増やす | 手づかみ・スプーン練習・おにぎりづくりなど“できた!”の経験を大切に。 |
| 🌸 感謝を伝える | 「このお米は田んぼで育ったんだね」など、命をいただく意識を少しずつ育てる。 |
こぼしても大丈夫。成功よりも「挑戦したこと」を認めてあげましょう😊
👉 関連記事:【2025年無添加】体にいいお菓子、スーパーやコンビニですぐに見つける方法
(甘いおやつも食育の時間に変わります)
3-2 小学生低学年(6〜8歳)|「自分で選ぶ」喜びを育てる
低学年になると、食に対して自分の好みや意思が出てきます。
この時期は「自分で選ぶ」経験を増やし、主体性を育てる食育が効果的です。
| 食育のポイント | 内容 |
|---|---|
| 🥕 買い物を一緒にする | 生協カタログやスーパーで、どの野菜を買うか相談してみる。 |
| 🍚 簡単な調理に挑戦 | おにぎり・サラダ・味噌汁など、火を使わずできる調理を体験させる。 |
| 💬 味の違いを話す | 「この塩の方がまろやかだね」など、味覚を言葉で表現させる。 |
👉 関連記事:【2025最新版】スーパーで買える無添加食品ランキング|保育士ママが選ぶ安心・安全なおすすめ商品
👉 関連記事:【2025年最新版】安全な油の選び方|スーパーで買える無添加オイルまとめ
「どれがいい?」と聞くだけでも、自立への第一歩になります🌱
3-3 高学年以降(9〜12歳)|考えて選ぶ“食の自立”を育てる
高学年になると、学校や友達との関わりも広がり、食の価値観も多様になります。
この時期は、“なぜそれを選ぶのか”を考える力を育てましょう。
| 食育のポイント | 内容 |
|---|---|
| 📖 食と健康の関係を知る | 「甘いものを食べすぎたらどうなる?」など、体とのつながりを話題にする。 |
| 🏫 社会とのつながりを学ぶ | 食材がどこから届くか、生産者の話を知る機会を作る(生協の資料も活用)。 |
| 🍴 調理・片付けの全体を体験 | 家族の一員として、献立を考えたり片付けまで行う経験を重ねる。 |
👉 関連記事:【パルシステムとコープの違い】保育士ママが30年使って比較!子育て家庭に合う宅配はどっち?
この経験が、思春期の心を支える力にもなります
🌸まとめ|年齢に合わせた関わりで“食べる力”を育てよう
| 年齢 | 食育の目的 | キーワード |
|---|---|---|
| 幼児期(2〜5歳) | 五感で感じる楽しさ | 感覚・発見・遊び |
| 小学生低学年 | 自分で選ぶ喜び | 主体性・味覚・体験 |
| 高学年以降 | 考えて選ぶ自立 | 理解・感謝・責任感 |
年齢が上がるほど、子どもは「教えられる」より「任される」ことで伸びます。
家庭での食育は、親が見守り、子どもが挑戦する時間です。
一緒に食卓を囲むことが、何よりの学びになります。
親子で一緒に食を楽しみながら、心と体を育てていきましょう😊
家庭でできる!楽しく続く食育アイデア5選
食育は、「教える」ものではなく「一緒に楽しむ」もの。
家庭の中でも、少しの工夫で毎日の食卓が“学びの時間”になります。
ここでは、親子で無理なく続けられる5つの食育アイデアをご紹介します。
どれも実際に私が保育現場や家庭で実践してきた方法ばかりです。
4-1👩🍳 親子クッキングを楽しもう
料理を一緒にすることは、最も身近な「生きる力」を育てる食育です。
包丁を使わなくても、混ぜる・並べる・盛りつけるだけでOK。
たとえば──
-
朝ごはんにサラダを盛りつける
-
おにぎりを一緒に握る
-
休日にお弁当を作ってみる
少しの失敗も成長のステップです😊
👉 食育と遊びが一体になった教材もおすすめです。
これらの教材は親子での“対話型クッキング”を自然に作り出してくれるので、
「食べる力」と「考える力」が同時に育ちます。
4-2🥕 野菜を育ててみよう
「食べものがどう育つのか」を知ることも、立派な食育です。
プランター1つでも、野菜を“育てて食べる”経験は子どもに強い印象を残します。
■野菜を育てる食育
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 🌱 身近な野菜から始める | ミニトマト・ラディッシュ・バジルなど、成長が早く観察しやすいものがおすすめ。 |
| 👀 観察と記録を楽しむ | 「芽が出たね」「今日は雨だったね」と声をかけて、観察力を育てる。 |
| 🍴 収穫したら一緒に食べる | 自分で育てた野菜の味は格別!苦手克服にもつながります。 |
👉 参考:
自然に感謝の心も育ちます。
4-3📚 食育絵本・図鑑で学ぶ
食に興味を持ち始めたら、絵本や図鑑も取り入れてみましょう。
視覚から入る情報は、子どもの記憶に残りやすいです。
■おすすめの絵本・図鑑:
| タイトル | 特徴 |
|---|---|
| 『やさいのおなか』(福音館書店) | 切った野菜の断面を見て当てっこ遊びができる人気絵本。 |
| 『おべんとうバス』(ひさかたチャイルド) | 食べものを“キャラクター”として覚えやすい。 |
| ビジュアル食べもの大図鑑 食の情報まるわかり!(金の星社) | 食材のルーツや栄養を親子で学べる。 |
4-4🧂 “味見ごっこ”で味覚を育てる
味覚教育は、小さな“味の体験”の積み重ねです。
同じ料理でも、塩・だし・油を変えるだけで味が全く違うことを、親子で感じてみましょう。
| テーマ | 例 |
|---|---|
| 塩の違い | 天日塩と精製塩を味見して「どっちがまろやか?」と話す。 |
| だしの違い | 鰹・昆布・煮干しで風味を比べて、好きな香りを見つける。 |
| 油の違い | オリーブ油とごま油を比べて、香りや舌ざわりの違いを感じる。 |
👉 関連記事:
味覚を育てることは、五感と心を育てることでもあります🌿
4-5 🍽️ 食卓での「ありがとう」を習慣に
食事は、命と人とのつながりを感じる時間です。
「作ってくれてありがとう」「おいしいね」と言葉にすることで、
食への感謝と家族の絆が自然に深まります。
■食への感謝・人への感謝
-
食材を作った人への感謝
-
作ってくれた人への感謝
-
食べられることへの感謝
この3つの“ありがとう”が、子どもの優しさと自己肯定感を育てます。
👉 関連記事:【子供の食事の悩み】好き嫌いを克服するための5つの工夫で、食事を楽しくしていきましょう
👉 関連記事:子どもの自己肯定感を高めるためには?親が忘れたくない子どもが育つ7つの接し方
👉 関連ポスト:X投稿|「見守る子育て」シリーズ(@tumikitosuzu)
それこそが、毎日の食卓からできる“心の食育”です。
■🌿まとめ|楽しみながら“食べる力”を育てよう
| アイデア | 育つ力 | 関連キーワード |
|---|---|---|
| 親子クッキング | 自立心・達成感 | 食育 親子・子ども 料理 |
| 野菜を育てる | 観察力・感謝 | 家庭菜園・食育 体験 |
| 食育絵本 | 想像力・知識 | 食育 絵本・図鑑 |
| 味見ごっこ | 五感・判断力 | 味覚教育・無添加 |
| 「ありがとう」習慣 | 思いやり・共感 | 家族 食育・心の教育 |
食育の本質は、「食べることを通して生きる力を育てる」こと。
日常の小さな工夫が、子どもの一生の財産になります🌸
忙しい家庭でもできる!時短×安心の食育サポート
共働きや子育てで忙しい家庭では、
「食育をしたいけれど、時間がない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
でも、食育は“完璧にやること”ではなく、“日々のごはんを大切にすること”から始まります。
最近は、食材宅配サービスを上手に使うことで、
「時短」と「安心」を両立した食卓づくりができるようになっています。
5-1 共働き家庭が無理なく実践する「食材宅配」の活用法
食材宅配は、“料理を時短しながら栄養を整える”頼もしい味方です。
買い物や献立の手間を減らしつつ、安全な食材を自宅に届けてくれるので、
共働き家庭でも無理なく「食育のある暮らし」が続けられます。
| サービス名 | 特徴 | こんな家庭におすすめ |
|---|---|---|
| 🥕 オイシックス(Oisix) | 有機野菜・無添加調味料中心。15分で完成するミールキットが人気。 | 忙しくても“手作り感”を大切にしたい家庭 |
| 🧺 コープデリ(生協) | 食材だけでなく冷凍惣菜や離乳食も充実。安全基準が厳しい。 | 家族全員の食事をまとめて安心したい家庭 |
👉 関連記事:
それも立派な“食育”の形なんです😊
5-2 無添加・栄養バランスの取れた食品で“安心して任せられる”仕組み
オイシックスもコープデリも、添加物をできるだけ使わない食品づくりを徹底しています。
特に、生協は30年以上利用している私の実感としても、
「忙しくても、子どもに安心して食べさせられる食材」が揃っています。
| 観点 | オイシックス | コープデリ |
|---|---|---|
| 安全基準 | 農薬・添加物の厳しい自主基準 | 国の基準+生協独自の検査 |
| 栄養バランス | 管理栄養士監修のレシピ付き | 離乳食・幼児食まで一貫対応 |
| 使いやすさ | 調理10〜15分のミールキット | 毎週決まった日時に届く安心感 |
👉 関連記事:
ママもパパも子どもとの時間を心から楽しめます🌱
5-3 家族の食卓を「整える」ことが最大の食育
「手作り」や「無添加」にこだわることも大切ですが、
本当に大切なのは、“家族が一緒に食卓を囲むこと”です。
たとえ冷凍おかずの日でも、
-
「今日も一緒に食べよう」
-
「おいしいね」「ありがとう」
この言葉を交わす時間こそが、子どもの心を育てる“食育”の本質です。
家族の心が落ち着く場所を作ること。
それが毎日の“心の栄養”になります。
■🌿まとめ|忙しくても“食育のある暮らし”はできる
-
食材宅配は、忙しい家庭の食育をサポートする強い味方
-
無添加・安全基準が高いサービスを選べば安心
-
食卓を整える時間が、子どもの心と体を育てる
| サービス | 特徴 | 関連記事 |
|---|---|---|
| オイシックス | 有機野菜・無添加・時短キット | Oisix詳細はこちら |
| コープデリ | 家族で使いやすい総合食材宅配 | コープデリの口コミと使い方 |
家庭でできる“食育”は、
忙しさの中でも心のゆとりを取り戻す時間になります。
子どもの笑顔と家族の健康を守るために、
今の暮らしに合った「安心の仕組み」を取り入れていきましょう🍴
モンテッソーリ教育に学ぶ|家庭でできる“食育の環境づくり”
食育の基本は、「子どもを信じて、やってみる機会を与えること」。
モンテッソーリ教育では、「子どもは自分で育つ力をもっている」と考えます。
その力を引き出すために大切なのが、
大人が“手を出しすぎず、整えすぎない環境”をつくること。
いちばんの学びの場です😊
6-1 環境を整えることから始めよう(子どもサイズを意識)
モンテッソーリ教育では、環境づくりがすべての基盤です。
子どもが“自分でできる”ように、道具や家具を子どものサイズに合わせることから始めます。
| 例 | ポイント |
|---|---|
| 🍽️ 食器・コップ | 割れても大丈夫な小さめの陶器を。重さ・手触りから学ぶ経験に。 |
| 🪑 テーブル・椅子 | 足が床につく高さで。姿勢が安定すると集中力が上がります。 |
| 🥄 調理道具 | 子ども用包丁・小さなまな板で安全に「まねっこクッキング」。 |
💡子どもが届く高さに物を置くことで、「やってみよう」という意欲が自然に生まれます。
環境が整えば、声かけよりも先に、子どもが自分で行動できるようになります。
👉 関連記事:
子どもがご飯を食べてくれないと疲れますね、そんな時の対応を現役保育士がまとめました
6-2 子どもは“やって学ぶ”存在
子どもは、「見て、聞いて、やってみて」初めて理解します。
大人が説明するよりも、実際の体験がいちばんの学びになります。
| 体験 | 学べること |
|---|---|
| 🥬 野菜を洗う | 感触・冷たさ・においから五感を育てる。 |
| 🍚 ごはんをよそう | 分量の感覚や“できた”という自信が育つ。 |
| 🍴 食器を並べる | 順序や美しさへの感性が養われる。 |
自分の手で触れ、試すことを通して、本当の理解が深まります🌿
6-3 “自分で選ぶ”ことで責任と意欲が育つ
モンテッソーリ教育では、「自分で選ぶ経験」がとても大切にされています。
食の場面でも、小さな選択の積み重ねが子どもの自立心を育てます。
| シーン | 声かけの例 |
|---|---|
| 朝食のパンを選ぶ | 「今日は食パンとロールパン、どっちにする?」 |
| 野菜を盛りつける | 「このトマト、どこに置こうか?」 |
| おやつを選ぶ | 「今日はクッキーとアイス、どっちにしよう?」 |
👉 関連記事:【2025年無添加】体にいいお菓子、スーパーやコンビニですぐに見つける方法
選ぶことで「自分の行動に責任をもつ」感覚が芽生えます。
これは食だけでなく、生き方そのものの基礎になります。
6-4 “繰り返す”ことで力が定着する
子どもは、新しいことを繰り返すのが大好きです。
同じことを何度もやるのは、飽きているのではなく、理解を深めている証拠です。
たとえば──
-
おにぎりを何度も握りたがる
-
野菜を切る作業を毎日したがる
-
テーブルを拭くのを自分の役目にする
大人はつい「もういいでしょ」と止めてしまいがちですが、
その繰り返しの中に“集中力”と“達成感”が生まれています。
大人が「待つ力」を持つことで、子どもは安心して成長できます🍚
6-5 大人は“見守り”ながら、必要なときだけ手を添える
モンテッソーリ教育では、大人は「教える人」ではなく、「見守る人」。
食育の場でも、子どもが自分でできるように導く“環境のガイドとして関わります。
| 大人の関わり方 | 効果 |
|---|---|
| 🌸 指示よりも提案をする | 「手伝ってみる?」など、選ぶ余地を残すと主体性が育つ。 |
| 🕊️ 失敗を責めない | こぼす・落とす経験も学び。自信を奪わない。 |
| 🌿 結果より過程を褒める | 「がんばったね」「ていねいにできたね」と努力を認める。 |
👉 関連ポスト:X投稿|「見守る子育て」シリーズ(@tumikitosuzu)
■🌿まとめ|“整える・任せる・見守る”が、家庭の食育の基本
| キー | 子どもの力 | 大人の関わり |
|---|---|---|
| 環境を整える | 自発性が育つ | やってみたくなる場を用意する |
| やって学ぶ | 感覚・集中力が育つ | 結果より過程を見守る |
| 選ぶ・繰り返す | 判断力・自信が育つ | 成功・失敗を一緒に喜ぶ |
子どもは、大人が思う以上に自分の力で育つ存在です。
食卓を「教える場」ではなく「一緒に育つ場」に変えていきましょう🍴
子どもが自分のペースで伸びていく姿を見守れるようになります。
毎日の食事時間が、親子の信頼を深める最高の時間になります🌸
🌿まとめ|“整える・任せる・見守る”が、家庭の食育の基本
モンテッソーリ教育の考え方を家庭の食育に取り入れることで、
子どもは「やりたい」気持ちを行動に変え、自立と感謝を自然に学んでいきます。
| 観点 | 子どもの力 | 大人の関わり方 |
|---|---|---|
| 🏠 環境を整える | 自発性が育つ | 子どもサイズの環境を用意する |
| 🍚 やって学ぶ | 感覚・集中力が育つ | 手出しせず“見守る勇気”を持つ |
| 🌿 選ぶ・繰り返す | 判断力・自信が育つ | 成功・失敗どちらも肯定的に受け止める |
家庭の食卓には、
「自分で考える力」「感じる力」「感謝する心」を育てるヒントが詰まっています。
そしてそれは、特別なことをしなくても、
毎日のごはん時間の中で少し意識を変えるだけで実践できます。
■🍴 たとえば、こんな風に少しずつ取り入れてみましょう
-
素材を知る時間を作る →
👉 スーパーで買える安全な天然塩おすすめランキング10選
👉 【2025年最新版】安全な油の選び方|スーパーで買える無添加オイルまとめ -
忙しい日も安心して食卓を整える →
👉 30年使ってわかった!コープデリの無添加食品おすすめ26選 -
おやつの時間も“学びの時間”に変える →
👉 【2025年無添加】体にいいお菓子、スーパーやコンビニですぐに見つける方法
これらの記事を参考に、
「安全な食×子どもの自立」という軸で生活全体を見直すと、
モンテッソーリ教育の考え方が自然に家庭の中に根づいていきます。
大人が整え、任せ、見守ることで、
親子の時間がもっとあたたかく、豊かになります🍀
最後までお読みいただき、ありがとうございました。