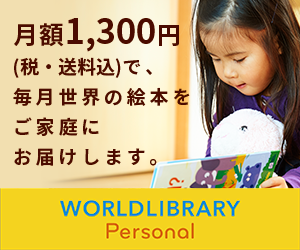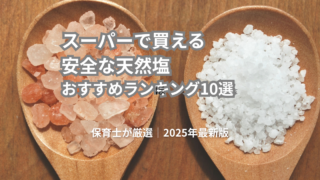という 疑問に対してー
モンテッソーリ教員としての経験、私の子育てと 保育士・学童支援員の経験からお手伝いについてまとめました。
この記事を読んでわかること
1,子どもがお手伝いをやりたくなる方法
2,子どもがお手伝いをするメリット
3,子どもがやる気をだすためのお手伝いアイテムは何か
4,イライラしないで、子どもにお手伝いをさせるポイントについて
5,子どもにお手伝いをさせる年齢と内容の目安
・これから子どもがお手伝いをやらせていきたいがどうしたらいいか悩んでいる方
・子どもとかかわっている方、
にお届けします。
ワーママにとってはただでさえ忙しい毎日です。
はじめのうちは、手間取ることがあっても、お手伝いをしてくれると、本当に助かると実感できる時が来ます。
私の子どもが小さい時もそうでした。
やりたい時期を逃すと家事には興味を持たなくなってしまいます。
子どもにも伝えて、ママやパパも子どもも家族みんなで、家事をしていきましょう!
スポンサーリンク
目次
子供のお手伝い、やる気が出る5つの方法

成長発達に伴い、子どもが『自分でやってみたい』という気持ちが出ていきます。
わかりやすくやり方を教えてあげましょう。
【おうちモンテ】家庭で自己教育力を高める育児のコツ9選、子どもが一人でできるためには
それでは、子どもがお手伝いをやりたくなる5つの方法はー
- やり方をゆっくり示してやってください
- できるようになるまで、待ってあげましょう
- 子ども専用の道具を用意すると子どもは積極的に取り組みます
- 家族の前で認めてやりましょう
- 家族みんなが役割をもつようにします
1,やり方をゆっくり示してください
- これ以上ゆっくりできないくらいの早さで見せましょう
- 言葉はなるべく使いません。動作で示してやる方が、子どもにはわかりやすいでしょう。
- 作業には段取りがあるところから見せて、何かをする時は順序があることを教えます。
2,できるようになるまで、待ってあげましょう
- 間違えても「違うよ」の声掛けでなく、「もう1度やってみるから、見ていてね」と言って、ゆっくり繰り返して見せてあげてください。
- 何回もやって見せる
3,子ども専用の道具を用意すると積極的に取り組みます
- 子どもの手のサイズに合ったものが使いやすい(ふきん、エプロンなど)
- 本物であること(包丁や、まな板など)
4、家族の前で認めてやりましょう
- 人の役に立つことを誇りに思えるような言葉かけをする「ありがとう」「たすかったよ」
- 家族の前で、できたことを話題にする
- 結果にこだわらないで、やろうとした気持ちを大事にする
5、家族みんなが役割をもって楽しみましょう
- 子どもが興味をもつためには、手本となるよう、大人もポジティブに家事をする
- 家族みんなが、何らかの役割をもって担当する
- 大人もうまくできたら喜び、家族で共感しあう
やる気がでる子供のお手伝い、5つのメリット

ここで、子どもがお手伝いをすることで、どんな効果があるのかあげてみます。
- 「できた」という達成感をいだきます
- 親子のコミュニケーションが増えていきます
- 道具を使いこなす器用な手になります
- 集中力がつきます
- 自己肯定感をもつようになります
1,「できた」という達成感をいだきます
- はじめからうまくはできません。そこを乗り越えて何度も挑戦してやりとげます。
- 家族の喜ぶ顔を見て、やれたという気持ちになります。
2,親子のコミュニケーションが増えていきます
- 子どもがやりたそうにしている時や、やってみようかと迷っている時に子どもの気持ちを聞きます。 「やってみる?」
- やり方をやって見せたり、やり方を伝えていきましょう。
- 共感する言葉のやりとりが増えていきます。
3,道具を使いこなす器用な手になります
- たたむ・しぼる・拭く・混ぜる・切る・掃くなどの仕事には、つまむ・にぎる・まわす・しぼるなど 手や指先をたくさん使います。
- 道具を使う時には、力の調節が必要です。そういうことを自分で体得していきます。
4,集中力がつきます
- やりかたを教わる時、よく見るようになります。
- ていねいに最後まですることの大事さがわかってきます。
- 自分でよく考えようとしてきます。
- けがをしないように、こぼさないように、慎重になる時間を持てます。
- 物に対して、大事にする気持ちや愛おしむ気持ちが出てきて、無駄にならないように精いっぱい集中するようになります。
5,自己肯定感をもつようになります
- みんなの役に立った、自分も家族の一員だということを実感するようになるでしょう。
- 家族から認められることがふえていきます。
- 家事を手伝うことで、それが生活習慣となって、行動も気持ちも自立していきます。
子供のお手伝い、やる気が出るお手伝いアイテム
『大人が毎日している家事に興味を持つ』
『自分もやってみたい』などは
その作業と共に、子どもにとっては道具も魅力的です。
子どものやる気スイッチを押してくれるお手伝いアイテムをご提案します。
- エプロン(できれば、自分自分で着脱できるもの)
- 子どもサイズの道具(フキン、雑巾、スポンジ、ほうき、ジョーロなど)
- 子どもサイズのマイ包丁
- 棚やタンスに収納場所がわかる表示、マーク
子どもの成長や発達に合わせて、道具をリニューアルしていくと、またやる気が出てきます。
お手伝いアイテムの収納場所も親子で話し合い、積極的にお手伝いができるよう工夫しましょう。
1,エプロン
できれば、自分で着脱できるものが好ましいでしょう。
収納場所を決め、使い終わったらどうするのかを伝えておきます。
スポンサーリンク
2、子どもサイズの道具
- フキンやスポンジなどは、子どもの手のサイズに合わせ、縫ったり、切ったりなどして準備します
- ジョーロは、子どもが水を入れて運べるサイズにしましょう
スポンサーリンク
3,子どもサイズのマイ包丁
- 包丁は、よく切れなければ、かえって危険です。
- よく切れる、本物の包丁を準備します。
- 子どもの手に合ったサイズのものがあるといいでしょう。
スポンサーリンク
4,棚やタンスに収納場所がわかる表示、マーク
- 道具を使うためには、収納場所を知っておく必要があります。
- 使いたいものがどこにあるかわかりやすくするために表示するのもいいでしょう。
- 洗濯ものなど、たたんだ後にどこにしまうかが分れば、片付けまで手伝うことができます。
スポンサーリンク
イライラしないで、子供にお手伝いをさせるポイント

子どもに何かしてもらうと、かえって面倒なことも起こります。
散らかってしまったり、こぼしたり、汚れが取りていなかったり…。
しかし、やればやるほど上手になっていきます。
そこで、イライラしないで、子どものやる気を見守るポイントをお伝えします。
- 子どもが自分でやるという体験を大事にする
- 子どもを尊重する
- 子どもの成長にあった環境を考える
イライラして余裕がない子育て、子供とスローライフな生活で改善させましょう
1,子どもが自分でやるという体験を大事にする
子どもは、自分の感覚器官を実際に使うことでいろいろなことを学んでいきます。
何かができることも大事ですが、子どもにとっては、どのようにしてやるのか、その過程に興味があり、ていねいにやっていきたいところです。
その過程が分れば、その後に育まれる想像力が一段とかわってくるでしょう。
【モンテッソーリ教育とは】おうちで実践、7つの方法で子育てに安心感を
2,子どもを尊重する
尊敬と思いやりとを持って、子どもに接しましょう。
はじめは失敗したり、何度も同じことで間違ったりするでしょう。子どもに限ったことことではありません。
子どもにとって難しい所をなるべくゆっくりと、心を込めて繰り返しやって見せてください。
3,子どもの成長にあった環境を考える
人的環境
繰り返しチャレンジできると、前向きに物事に向き合うようになります。
まわりの大人の、「見ててやるからやってごらん」という構え方が、
子どもにとってはやる気が出ます。それと同時に大人にとっても、そのやる気を支えてあげたい気持ちが大きくなるでしょう。
物的環境
- 道具は子どもに合ったサイズのもの
- 体に合わせて踏み台を用意する
- 道具は、子どもの取り出しやすい場所で、いつも同じ所に置くようにします。
子供のお手伝い、やる気が出る年齢別おすすめ家事
子どもは、大好きなお母さんやお父さんが、料理・掃除・洗濯などのかじをステキにやっているのを見て、あこがれを抱いています。
「お母さんってやっぱり上手だな」「やってみたいなあ」………。
つまり、子どもが興味を持った時が、はじめる時!
「子どもはやりたいというけど、この時期にやらせるのはどうかな?」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
お手伝いは、子どもの興味がでた時に始めるのが一番ですが、目安を知りたいという方のために年齢別のおすすめ家事をあげてみます。
成長や発達・興味によって違いはありますが、子どもの年齢のめやすとお手伝いの種類はー
| 1歳 | ごみ捨て、くつ並べ、おもちゃの片付け など |
| 2歳 | お箸並べ、テーブル拭き、花の水やり、タオルなど洗濯物たたみ |
| 3歳 | 野菜洗い、食後の食器運び、ごみ拾い、花の水替え、窓ふき |
| 4歳 | 簡単な調理、米とぎ、こぼしたものを拭く、玄関の掃き掃除 |
| 5歳 | 野菜の下ごしらえ、包丁を使う料理、ゴミ出し、部屋の掃き掃除 |
| 6歳 | ピーラーを使う料理、コップ洗い、ゴミ出し,掃除機かけ、食器洗い |
| 7・8歳 | 包丁を使う料理、風呂そうじ、洗濯物干し、洗濯機で洗濯、 洗濯物たたみ・収納、上履き洗い、ゴミ分別 |
詳しく見ていきましょう。
1・2歳 お手伝いに『興味津々』の時期
- 簡単な調理(こねる・まぜる)
- 食後の食器運び
- テーブル拭き(食事前後)
- お箸並べ
- 家族分の配膳
- おもちゃの片付け
- ごみ箱にごみを入れる
- ごみ拾い
- 靴並べ
- こぼしたものを拭く
- 花の水やり
- 簡単な拭き掃除
- 簡単なせんたたみ(タオルなど)

3・4歳 お手伝いに『いろいろチャレンジ期』
- 簡単な調理
- 卵をわる

- 料理の手伝い
- 野菜洗い(じゃがいも・にんじんなど)
- 野菜の皮むき

- 米とぎ
- ごはんをよそう
- 食後の食器運び
- お箸並べ
- 家族分の配膳
- おもちゃの収納
- ゴミ箱にゴミを入れる
- ごみ拾い
- ごみ捨て・リサイクル分別
- こぼしたものを拭く
- 拭き掃除(床・窓)
- はき掃除(玄関)
- 簡単な洗濯物たたみ・収納
- 簡単な洗濯物干し(タオルなど)
- 花の水替え
5・6歳 お手伝いが『レベルアップする』時期
- 野菜の下ごしらえ(豆のすじ取りなど)
- 包丁を使う料理

- ピーラーを使う料理
- 食器洗い(コップ洗い、すすぎのみ)
- ゴミ出し
- 掃除機かけ
- お風呂そうじ
- 洗濯物干し(全般)
7・8歳 『一人でできるものが増える』時期
お仕事が上手になり、任せられるようになります
- ご飯炊き
- 火を使う簡単な調理
- 食器洗い(全般)
- 食器拭き・収納
- ゴミ出し
- 掃除機をかける
- 風呂そうじ

- 洗濯機で洗濯
- 上履き洗い
まとめ

この記事では、次の5項目についてまとめました。
1,子どもがお手伝いをやりたくなる方法
2,子どもがお手伝いをするメリット
3,子どもがやる気をだすためのお手伝いアイテムは何か
4,イライラしないで、子どもにお手伝いをさせるポイントについて
5,子どもにお手伝いをさせる年齢と内容の目安
子どもの成長には、お手伝いは大きなポイントになります。
また、家族の一員として、家族みんなで家事を進めることは大切なことです。
子どもにお手伝いをさせるうえで、失敗は多く、イライラすることもあるでしょう。しかし、発達途上と思って、尊重するべき人と受け止め、ゆっくり見守っていっていただきたいと願っております。
きっと子どもの幼いころから、いろんなお手伝いをさせておいてよかったと振り返って思う日が来ることでしょう。
子どもが料理を始める食育については、

最後まで読んでいただきありがとうございました。感謝しております。
スポンサーリンク